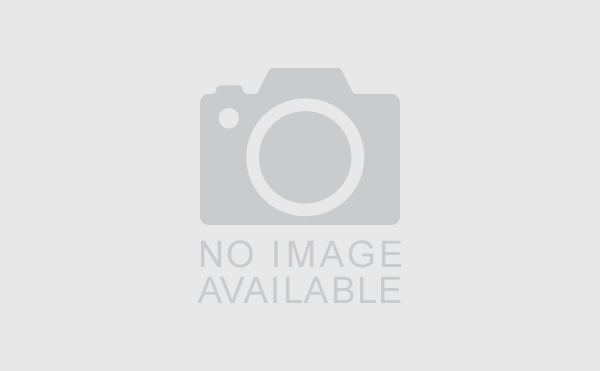6月29日
こんにちは。東京はもう梅雨入りして、雨が続いています。
先週は、『素数の積』についての出題でした。
と、訂正です。
誤:異なる2つの素数の積を何と言う?
正:2つの素数の積を何と言う?
申し訳ございませでした汗
答えから言ってしまうと、②の半素数でした。
素数の半分の役割をなしているって感じですかね。面白い名前です。
さて、今日の話題です(無理やり)。
.....なんで、梅雨って起こるんでしょう。雨ばっかりで憂鬱な気分になります...(-_-;)
んまあ、言ってしまえば梅雨ってのは夏になるために必要な時期なんですよね。メカニズムがちゃんとあります。
日本の周りには、4つ、気団があります。気団というのは、ざっくり言えばものすごく大きい空気の塊です。
具体的に言えば、「オホーツク海気団」、「シベリア気団」、「小笠原気団」、「陽子江気団」なんですが、それは置いといて、初夏になってくると、この中の2つの気団(オホーツク海気団と小笠原気団)が発達してきます。そして、オホーツク海気団は冷たく、小笠原気団は暖かいです。
気団が膨らんできて、いわゆるぶつかり合いが起こってしまうんですね。
詳しい原理は割愛しますが、気温が違う気団がぶつかり合うと、前線の完成です。
気団の境界線を、『梅雨前線』という名前で飾り付けている(?)んですね。
ちなみに、地球の前線は4つに分けられ、梅雨前線は「停滞前線」という前線の特別版みたいなものですね。
さて、今回はそんな梅雨前線からの出題です。
西日本では、気温ではなく、別のなにかの違いがはっきりしているようです。それはなに?
①水蒸気 ②気圧 ③におい
来週も張り切っていきましょう!