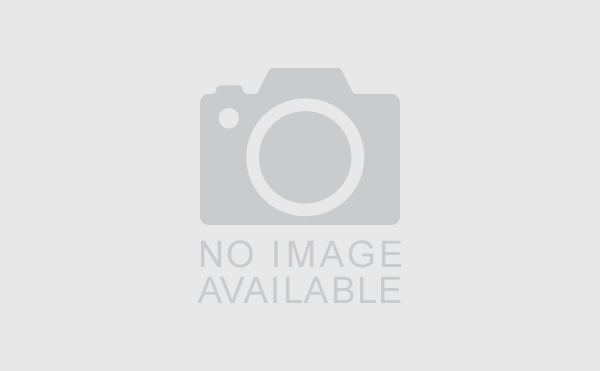10月18日
こんにちは。日が落ちるのがだんだん早くなってきましたね。
前回と前々回は擬似完全数を紹介しました。今回は約数の和の話からは遠ざかって、ウラム数というものを紹介します。1018はウラム数であり、この数はスタニスワフ・ウラムというアメリカの数学者が考案しました。
このウラム数の定義は少し複雑なので順を追って説明していきます。
そもそも、このウラム数は数列があるうえで成り立っています。ウラム数列に含まれればウラム数という具合に。
まずはじめに、数列に1と2を追加します。
$$1,2$$
次に、「数列の中にある異なる2つの数字を足した数」を次の項とします。数列の中には1と2しかないのでこれを足して3になります。
$$1,2,3$$
さて、次も数列の中から2つ選んで足すのですが、その足したあとの数にはこんな条件があります。
1.足したあとの数は選んだ2つの数の和でしか表せない
2.1のうち最小の数である
最初に条件1については、$a,b,c,d$という数列があって次の項が$e$だったとして、$e$が$a+d$もしくは$b+c$と表されるような状況であってはいけないということです。
$1,2,3$のなかから2つを取り出して足してできる数は3,4,5のどれかですが、3はもう数列にあるので除外します。4と5はどちらも1+3、2+3でしか表せませんが、そのうち最小の方は4(条件2より)なので、数列に追加します。
$$1,2,3,4$$
次に5を追加しようと考えますが、4が追加されると5は1+4とも2+3とも表されてしまうことになります。これでは条件1を満たさないので、5はウラム数列に含まれません。
ウラム数列は項のなかの2つを足すという点でフィボナッチ数列と似ていますよね。ただその2つに条件があるというところがフィボナッチ数列とは違って、少しフィボナッチ数列より複雑なものになっています。
ちなみに、はじめに紹介したスタニスワフ・ウラムは、モンテカルロ法やウラムの螺旋など結構有名なものを考えた人で、数学に広く貢献していたそうです。多くの分野に顔を出していてすごいです。
今日はウラム数について紹介しました。それでは来週一週間も楽しく過ごしていきましょう!